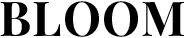高齢者のデジタルデバイド問題とは?対策方法などを解説
2023.05.13
日本では、65歳以上の高齢者は2021年9月時点で3,640万人、総人口に占める割合は29.1%と過去最高となっており、今後も増え続けていきます。
こうした中、高齢者のデジタルデバイドが注目されています。
今回は、高齢者のデジタル利用の実態やデジタルデバイド解消の取り組みなどについて解説します。
デジタルデバイドが進む高齢者の現状とは?
高齢者がデジタルツールやサービスを使う際に、どのような課題があるのか見てみましょう。
インターネットを使いこなせない
高齢者がデジタルを使いこなせないので、最新の情報にアクセスできるように、高齢者向けにFacebookの使い方のガイドを作成するといった動きがあります。
ですが、本来、サービスとは、マンツーマンのトレーニングなしで利用できるようにしなければいけません。
デジタル機器の保有率が低い
高齢者のデジタルデバイド問題が発生する原因とは?
では、なぜ高齢者のデジタルデバイド問題が発生するのか、原因について解説します。
デジタル機器が操作できない
正しい情報を見極められない
普段から、Webの情報に触れていると、怪しい情報を見極める能力が自然と身についてきます。
広告ブロッカーを使用したり、Cookieを有効にする選択ができたり、安全なアプリと怪しげなアプリの区別も感覚で分かる方は多くいます。
ですが、高齢者は、Webの情報に慣れていないため、スパムに騙されて、デバイスの情報を抜き取られたり、悪用されたりする恐れがあります。
このようなことから、高齢者がデジタル製品を遠ざけてしまっています。
小さいフォントやボタンが読めない
ボタンやフォントのサイズが小さいと、高齢者には、使いづらいです。
老眼のユーザーがモバイルデバイスを使うと、致命的な問題になるでしょう。
色のコントラストなど、高齢者の使いやすさを意識したデザインを心がけましょう。
デジタルデバイドが高齢者に与える影響とは?
生産性の低下
社会的な孤立
緊急時の避難の遅れ
高齢者のデジタルデバイドへの対策とは?
以下で見てみましょう。
高齢者にフレンドリーなデバイスの設計
ITリテラシーに関する教育
高齢者にパソコン教室を開く
ITツールを使って、コミュニケーションをする
まとめ
新型コロナウイルスの流行によって、課題とされていた高齢者のデジタルデバイド問題が注目されています。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
オフィス代を安く済ませるために、自宅住所をビジネスの住所にする方もいるでしょう。
ですが、自宅住所をビジネスの住所にしてしまうと、情報の漏洩やトラブルに巻き込まれるリスクが生じます。
「このようなトラブルに巻き込まれたくない」とお考えの方は、バーチャルオフィスを利用するといいでしょう。
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。
ブルームで住所を借りれば、プライバシーをしっかりと確保することができます。
また、ブルームの月額料金は、300円~のため、オフィス代を節約したい方にとってはベストな選択肢になるでしょう。
オフィス代を抑えて、その余った費用を事業資金に回したい方は、ブルームの利用をぜひご検討ください。