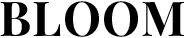デジタル・デバイドとは? 情報格差がもたらす課題
2023.04.06
情報通信技術の急速な進化にともなって、スマホ・SNS・クラウドなどが幅広く普及し、ライフスタイルやワークスタイルのさまざまな場面で大きな変化が見られています。
情報通信技術の進化は、デジタル化の流れに乗れている人とデジタル化の流れに取り残されている人も存在し、その格差も広がっています。
今回は、情報格差を意味するデジタル・デバイドの課題や発生原因、解決策について解説します。
デジタルデバイド(情報格差)とは?
企業でデジタルデバイドが発生する原因とは?
デジタルデバイドが発生する原因を見てみましょう。
デジタルデバイドを埋めるためには、あらかじめ対策しておく必要があります。
ITへの理解不足
IT人材の流出や不足
デジタルデバイドの問題点とは?
デジタルデバイドによる問題点を見てみましょう。
以下の問題の中で、自社に当てはまっているものがある場合は、早急に改善する必要があります。
業務効率の低下
競争力の低下
緊急時の対応遅れや犯罪が起こるリスク
自然災害・疫病拡大・テロなどの緊急時には、ICTによる高い情報収集能力があれば、状況を的確に判断できるため、適切な対応がとりやすいです。
ですが、ITリテラシーが備わっていないと、状況を把握しにくいので、緊急時の対応に遅れてしまい、被害を被ることもあります。
また、個人情報・ストーカー被害・クレジットカードの不正使用といったインターネットを介した犯罪に遭うリスクも負っています。
グローバル化への遅れ
デジタル・デバイドにより情報技術分野で後れをとっている企業は、グローバル化の波に乗れず、国際競争力が低下する恐れがあります。
テクノロジー・教育・労働・政治・観光など、さまざまな面において情報格差が発生することにより、国際経済や国際社会が抱える大きな問題へ発展することもあるでしょう。
デジタルデバイドを解決する対策とは?
IT化を実現しながら、デジタルデバイドを解決するための対策を解説します。
IT教育の質の向上
IT環境を少しずつ構築する
複雑なITツールを使わない
まとめ
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
バーチャルオフィスの住所を利用すると、法人登記する際や副業の際に、自宅の住所を公開する必要がないため、便利です。
また、バーチャルオフィスに届いた郵便物や宅配物を受け取って、指定住所への転送をしてくれるサービスもあります。
バーチャルオフィスが、自宅から離れた場所にあっても、手軽に郵便物の確認や受取ができるため、安心です。
ブルームは、住所利用・郵便物転送・法人登記サービスを提供しているバーチャルオフィスです。
東京都新宿区西新宿の一等地住所を、業界最安値の月額300円~レンタルしています。
コストをかけずに、安心安全に事業に集中したい方は、ブルームの利用を検討してはいかがでしょうか。