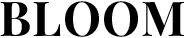脱ハンコの取り組みとメリット
2023.03.24
昨今、テレワークのように、会社に出勤しない働き方が広く注目されるようになりました。
ですが、実際のところ、テレワークをしている企業は3割以下ともいわれているのが実情です。
なぜ多くの企業がIT化やデジタル化がそれほど進んでないかというと、その理由の1つに、日本独自のハンコ文化による承認の押印などが弊害になっています。
そのような状況のため、働き方改革推進の重要なテーマとして、脱ハンコが注目されており、その実現のためのアプローチが企業で検討されています。
ハンコ文化は、日本のビジネス習慣に深く根付いていますが、近い将来、ビジネスシーンでハンコを見ることがなくなるかもしれません。
今回は、ハンコ文化が抱える課題と脱ハンコのメリット、そして脱ハンコを実現するためにはどうしたらいいかについてを解説します。
ハンコ文化が抱える問題とは?
まず、ハンコ文化が抱える問題が何なのか、見ていきましょう。
押印がないと、次の仕事に進めない
押印のために出社しなくてはいけないという事態が起こるのは、押印がないと仕事を進められないからです。
押印自体は会社に利益をもたらす業務ではないので、生産性のない業務を生みます。
押印前の根回し・押印してもらうまでの待ち時間・押印をするための出社・押印の確認などハンコのためだけにあらゆるタイムロスが発生するので、本来取り組むべき業務の時間が奪われ、生産性向上の妨げとなってしまうのです。
ペーパーレスが進まない
ハンコ文化は、ペーパーレス化を妨げます。
ハンコと紙によるワークフローをすると、書類のファイリング・ラベリングの管理業務・書類の輸送業務が必要になります。
また、文書の保管スペースが必要になるため、印刷・輸送コストなども発生します。
つまり、ハンコ文化とそれに伴うペーパーワークが、コストを増やす要因となっているのです。
押印のために出社する必要がある
押印するには出社しなければいけないため、テレワークを困難にしている要因になります。
脱ハンコのメリットとは?
では、脱ハンコを実現すると、どのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
業務の効率化
ハンコ文化をなくすと、無駄な手間が減り、業務効率化にもつながります。
押印をしてもらうために待つ時間・押印をするための出勤時間は、削減可能な時間ですし、それをなくしてしまえば、押印に付随する作業や業務も削減できます。
そうすると、無駄な時間を、本来の業務の時間に充てることができるので、プロジェクトを進めるスピードも速くなり、無駄が減って業務効率化につながっていくでしょう。
コスト削減
ペーパーレス化の実現で、ペーパーワークで発生していた紙代・印刷代・書類の保管庫代・輸送費などをカットすることが可能です。
テレワークのような多様な働き方の実現
ハンコの押印がなくなれば、出社する理由がなくなり、テレワークなどの柔軟な働き方が実現できます。
時間や働く場所にとらわれずに、確認や申請・承認をオンラインですることができ、テレワークなどの多様な働き方の導入もスムーズに進められるでしょう。
脱ハンコのために導入するシステムとは?
では、脱ハンコのために、どのようなシステムを導入したらいいのかを紹介します。
ワークフローシステムの導入
ワークフローシステムには申請フォームがあるため、申請をすれば、承認依頼を関係部署に自動的に送れます。
承認は、承認者がシステム上で処理をして、どの部署の誰が、いつ承認したのかという記録も残るのでトラブルになることもありません。
電子契約システムの導入
取引先との契約で必要となるハンコの代わりとなるのが電子契約システムです。
電子契約システムを使えば、作成した書類をインターネット経由で取引先に送信し、双方で電子文書に電子署名を付与することで合意が証明されるため、契約を締結できます。
まとめ
今回は、ハンコ文化が抱える問題・脱ハンコによるメリット・脱ハンコを実現するための取り組みについて解説しました。
脱ハンコは、生産性の向上につながりますので、業務効率をアップするためにも、取り組んだほうがいいです。
また、テレワークのような多様な働き方に対応するためにも、脱ハンコは不可欠です。
そのため、ハンコ文化からの脱却に向けて、システムを導入するなど、小さなできることから始めていくといいでしょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
オフィスを賃貸で借りると、物件を見た後に契約をするため、時間が非常にかかります。
ですが、バーチャルオフィスを利用する場合、そのような面倒な手間はいりません。
ブルームは、ウェブ上で契約手続きをするため、すぐに契約ができ、スピーディに事業開始することができます。
また、ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所を、業界最安値の月額300円~レンタルしており、圧倒的なコスパの良さが大きな強みです。
コストをかけずにすぐに事業を始めたい方は、コスパが非常にいいブルームの利用を検討してはいかがでしょうか。