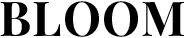勤務間インターバル制度とは?メリット・デメリット、導入方法などを解説
2025.10.21
2019年4月に施行された働き方改革関連法によって、勤務間インターバル制度が注目を集めています。
長時間労働を防ぎ、従業員の心身の健康を維持するために、国が導入を推奨しているのです。
今回は、勤務間インターバル制度の内容やメリット・デメリット、導入方法などを解説します。
勤務間インターバル制度とは
勤務間インターバル制度は、終業時刻から翌日の始業時刻の間に、一定以上の休息時間(インターバル)を設ける制度です。
残業で終業時間が遅くなった場合でも、一定の休息時間が確保されるので、長時間労働や健康被害の防止やワークライフバランスの向上につながります。
インターバル時間の確保によって、所定の始業時間を超えてしまった場合、以下の対応を取る必要があります。
・インターバル時間と翌日の所定労働時間が重なる部分は労働したものとみなす(翌日の労働時間は所定よりも短くなる)
・始業時間と終業時間を繰り下げる
・ある時刻を過ぎたら、残業を禁止し、インターバル時間と所定の労働時間が重複しないようにする
制度の罰則はないの?
2019年4月から、勤務間インターバル制度が導入されました。
努力義務にあたる制度のため、違反しても、法的な罰則はありません。
企業が運用ルールを決めて、現場に合った対応をしています。
勤務間インターバル制度のメリット
勤務間インターバル制度のメリットを挙げてみましょう。
ワークライフバランスの実現
勤務間インターバル制度を導入すると、労働者は睡眠時間を十分確保できるだけでなく、プライベートの時間を増やせます。
仕事とプライベートの切り替えができると、プライベートが充実するため、ワークライフバランスの実現に寄与します。
生産性が向上する
勤務間インターバル制度によって、プライベートの時間を充実させられため、従業員は、仕事へのモチベーションを高め、ミスを防ぐことができるため、業務効率が上がります。
また、従業員の業務効率がアップすると、会社全体の生産性の向上につながります。
優秀な人材を確保できる
勤務間インターバル制度は、労働者にとって魅力的な施策のため、採用活動において有利になるだけでなく、離職率の低下につながり、優秀な人材を確保できます。
勤務間インターバルのデメリット
今度は、勤務間インターバルのデメリットを挙げてみましょう。
コストがかかる
勤務間インターバルを実施すると、従業員の労働時間が減少します。
そのため、既存の従業員が業務に対応できず、それを補うために、追加の従業員を雇用する必要が出てきます。
ですが、新たに従業員を採用し、教育するには、コストがかかります。
業務フローを見直さなければいけない
勤務間インターバルによって業務が制限されると、業務を遂行できない可能性があります。
労働時間が制限されたせいで、自宅に仕事を持ち帰って、長時間労働をすれば、勤務間インターバル制度を設けた意味がなくなります。
こうした事態を防ぐために、導入前に、業務フローを見直すことが重要です。
勤務間インターバル制度の導入方法
勤務間インターバル制度の導入方法をご紹介します。
従業員の労働時間を把握する
就業規則で定められている勤務時間と、残業を含んだ実際の勤務時間を把握します。
時間外労働、休息時間、交代制勤務の現状、通勤時間、従業員のニーズなどを踏まえて、課題を考える必要があります。
就業規則を見直してインターバル時間を設定する
厚生労働省が推奨するインターバル時間は、9時間のため、インターバル時間は、8~12時間ほどを目安に設定します。
そこに、従業員の通勤時間や睡眠時間、プライベートの時間を配慮して、調整する必要があります。
調整した内容は、就業規則に反映し、従業員に周知することによって、制度を定着させます。
定期的に制度を見直す
定期的に制度を見直して、必要な場合、就業規則を修正します。
ですが、例外の規定はなるべく増やさずに運用するのが望ましいでしょう。
勤務間インターバル制度の助成金
厚生労働省は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小事業主に、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」という助成金を設けています。
一定の要件を満たした事業主に、助成金が支給されます。
以下で要件について見てみましょう。
支給要件
助成金を受けるには、支給対象になる事業主の要件を満たさなければなりません。
また、勤務間インターバル制度を導入するのに必要な研修やシステムの導入をするなど、支給の対象になる取り組みをする必要があります。
成果目標
助成金の支給対象になる取り組みとして掲げた、成果目標を達成する必要があります。
例えば、事業実施計画で事業主が指定したすべての事業場で、休息時間数が9時間以上11時間未満であるか、11時間以上の勤務間インターバルを導入して定着を図ることが挙げられます。
支給額
支給額は、インターバル時間数や取り組みの内容の成果目標の達成状況によって異なります。
休息時間数が9時間以上11時間未満の場合、制度導入にかかった費用の4分の3(最大50万円)、休息時間数が11時間以上の場合は、制度導入にかかった費用の4分の3(最大60万円)が助成されます。
新規導入に該当する取り組みがある場合、記載の上限額の2倍まで助成されます。
また、賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合、加算される金額は、指定した労働者の賃金引上げ人数によって異なります。
常時使用する労働者が30人超の中小事業主の場合は、15万円~上限240万円までで、常時使用する労働者が30人以下の中小事業主の場合は、30万円~上限480万円までとなっています。
申請方法
厚生労働省のホームページから、交付申請書や事業実施計画、36協定届など助成金の申請様式を取得して、交付申請をします。
交付の決定通知を受理したら、機器の購入や研修の実施など、事業実施計画の内容を踏まえて事業を行います。
事業が終了したら、支給申請書や添付書類を用意して、支給申請をします。
まとめ
勤務間インターバル制度は、従業員の健康増進など、さまざまなメリットがあります。
ですが、業務の見直しなどをする必要もあるため、自社にあったルールにすることが大切です。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
ビジネスをする際に、会社や店舗の住所を、どの都道府県にするか重要です。
47都道府県の中でも、東京都は、多くの企業が拠点を置いているので、一番信頼性が高いです。
開業したばかりの会社や個人事業主には、都心一等地に事務所を構えることはなかなか難しいですが、ブルームのバーチャルオフィスを利用すれば、比較的簡単に都心一等地の住所を借りられます。
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているサービスオフィスです。
月額300円から、住所レンタルなど、事業に必要なサービスを提供しています。
多くの地方在住の方も、顧客に安心感を与えるために、西新宿で起業しています。
業界最安値の費用で、都心一等地住所で事業を行いたい方は、ブルームの利用を検討してはいかがでしょうか。