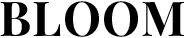コンピテンシーとは?その意味、コンピテンシーが注目される理由やメリットなどを解説
2025.09.02
昨今、生産性の向上や採用活動の強化のために、コンピテンシーを取り入れる企業が増えています。
コンピテンシーは、能力・資格・適性といった意味があり、ビジネスシーンでは、行動のもととなる価値観や思考、性格などを意味し、優れた成果を出すための重要な要素とされています。
今回は、コンピテンシーが注目される理由やメリット・デメリットなどを解説します。
コンピテンシーとは
コンピテンシー(competency)とは、能力・技能・力量・適性などの意味があります。
ビジネスシーンでは、コンピテンシーは、ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性と定義されています。
自社で高い成果を出している従業員のコンピテンシーを明らかにすると、自社で活躍できる人材を判断しやすくなる可能性があるのです。
そのためには、「いつもどのようなことを意識しているのか」「どういう理由で、どのように行動しているのか」といった自社のハイパフォーマーの思考や行動について分析する必要があります。
コンピテンシーが注目される背景
1970年代前半のアメリカで、米国文化情報局(USIA)の採用選考から、コンピテンシーという概念が生まれました。
従来の採用選考では、学歴や頭の良さが採用基準になっていましたが、学歴や頭がよくても、仕事ができるわけではないことが明確になりました。
そこで、採用選考のデータから調査をしたところ、優れた結果を出す従業員は、その行動に特徴があることが判明しました。
そのような状況で、採用基準に、行動を取り入れたことによって、コンピテンシーという概念が生まれました。
コンピテンシーと類似用語の違い
コンピテンシーと類似用語の違いを見ていきましょう。
スキルとの違い
スキルとは、従業員が持っている専門的な能力や技能のことです。
例えば、営業力やエンジニアリングの技術力などがあります。
スキルは、能力や技能のことですが、コンピテンシーは、能力や技能を発揮する力のことです。
そのため、コンピテンシーはスキルを活かして成果を出すための力と言えます。
ポテンシャルとの違い
ポテンシャルとは、その人に備わっている知力や特性のことです。
一方、コンピテンシーは、優れた結果を出す人の行動特徴のことです。
コンピテンシーを持っている人は、経験から高い成果を出すための行動の特徴を身につけたということもあるため、元から備わっているポテンシャルとは異なります。
ケイパビリティとの違い
ケイパビリティとは、企業やサービスが保有している組織的な強みや能力のことです。
組織を対象にしているか、個人を対象にしているかが、コンピテンシーとの違いになります。
アビリティとの違い
アビリティとは、先天的に与えられた能力や技量のことです。
一方、コンピテンシーは、アビリティを活かして成果を出すための力のことです。
コンピテンシーを活かせる場面
コンピテンシーを活かせる場面を挙げてみましょう。
採用と面接
人材の採用と面接をする際に、コンピテンシーは、採用基準を設定する際の指標の一つとして活用できます。
採用面接で、学歴や職歴を確認すると、どれくらいの知識やスキルを持っているかを確認できます。
ですが、自社でそれらの能力を活かせるかや、自社に適した人間性があるかを見極めるのは難しいです。
そのため、自社で活躍している従業員のコンピテンシーをもとに採用基準を作成することが有効です。
自社にあった行動特性を持っている従業員をモデルにすると、応募者が入社後に自社で活躍できるかどうかを見極めやすくなります。
面接では、実績だけでなく、どうしてその行動をしたのかを質問して、応募者の行動特性を確認するといいでしょう。
人事
コンピテンシー評価(コンピテンシーアセスメント)という手法で、コンピテンシーを人事評価に取り入れる企業が増えています。
コンピテンシー評価では、部署や階級の中で、優れた成果を出している従業員の行動を評価します。
「どのように行動して成果を出したのか」といったプロセスを評価するので、サポートをした従業員も評価することができます。
また、マーケットの要因や上司との相性などの曖昧な評価を取り除けるため、従業員のモチベーションが高まります。
マネジメント
部署によってコンピテンシーは、異なります。
例えば、A部署では、問題解決力の高い人が成果を出しやすい一方、B部署では、チームワークが重視されることがあります。
どのような行動が成果を上げやすいかがわかると、その特性を持っている従業員を適所に配置できます。
また、その部署やポジションで求められる行動をとらない人材を配置するミスマッチも防げます。
コンピテンシーを活用するメリット
コンピテンシーを活用するメリットを挙げていきましょう。
人材を育成しやすい
面接や評価に、コンピテンシーを取り入れると、人材育成がしやすくなります。
成果を出している従業員の行動特性を基準に評価や面接をするので、成果につながりやすい人材育成ができるからです。
モデルがいると、従業員は具体的に何をすればいいのかが把握できるため、企業が求める人物像に近づきやすくなります。
評価者が評価しやすくなる
人事評価をする時の評価基準が不明確であったり、納得できる評価をされないと、従業員のモチベーションが低下したり、不満を持つようになります。
ですが、コンピテンシーによる評価や面接を導入すると、評価基準が明確になるため、評価者は評価しやすくなります。
また、評価者によって評価結果が大きく異なることも起こりにくくなります。
評価が公平なため納得できる
コンピテンシー評価は、評価基準が明確なため、客観的評価をしやすく、従業員が納得できるでしょう。
評価結果によって、どうすれば評価につながるかを把握できるため、従業員のモチベーションアップにつながります。
人事戦略につなげることができる
コンピテンシーを導入すると、自社にどのような行動特性を持った従業員が必要なのかが明確になります。
自社のハイパフォーマーが持つ思考や能力を、募集要項に記載することで人事採用に活かせることができます。
また、どんな行動をすれば評価につながるかを具体的に従業員に伝えて、人材育成に活かすこともできます。
生産性が向上する
コンピテンシー評価は、パフォーマンスが高い従業員の行動特性から評価基準を決めるため、成功につながる行動パターンが明確になり、従業員間に相乗効果が出てきます。
そのため、高いパフォーマンスが発揮できない従業員に、コンピテンシー評価によって、潜在能力を気づかせることによって、従業員の生産性が向上し、組織全体の業績の向上が期待できます。
コンピテンシーの注意点
ここでは、コンピテンシーの注意点を挙げてみましょう。
コンピテンシーを導入するかどうかの検討をしてから、実際に運用をするまでに時間がかかります。
また、優れた結果を出す従業員の行動特徴を、あらゆる観点から調査することも重要です。
さらに、調査後にデータを分析して、従業員の模範になる特性をまとめる必要もあります。
コンピテンシーの導入の流れ
コンピテンシーの導入の流れについて見ていきましょう。
ハイパフォーマーにヒアリングをする
社内で高い成果を上げている複数の従業員からヒアリングをして、共通項を分析しましょう。
モデルになる従業員は、コンピテンシーを導入したい部署や役職から選びます。
成果は、売上達成率や受注率といった具体的な数字や客観的な事実に基づいて判断することが大切です。
モデルの従業員を選んだら、それらの従業員に客観的な事実を聞くために、アンケートやインタビューをします。
ヒアリングが終わったら、ハイパフォーマーにどのような行動特性がみられるのかを分析しましょう。
コンピテンシーモデルを作る
優秀な従業員に共通な行動特性を明確にして、コンピテンシーモデルに落とし込みましょう。
コンピテンシーモデルとは、高い変革志向性があり、組織やチームワークに優れている人のことです。
このようにすると、人事評価項目を設定しやすくなるでしょう。
人事評価項目を作る
コンピテンシーモデルをもとに、評価対象者に合った適切な人事評価項目を設定しましょう。
コンピテンシーモデルに沿ってペルソナを作成する必要があります。
ペルソナとは、目標となる架空の人物のことで、自社で高い成果を上げる理想の従業員をイメージしたもののことです。
ペルソナを決めると、評価対象者に求めるべき要素が明確になるでしょう。
人事評価項目を設定する
評価しやすくするために、人事評価項目を5段階に分けて設定しましょう。
5段階でレベルとは、以下の通りです。
[レベル1・・・受動行動]
自発的に動かず、指示があった時に動くので、周りから行動特性として認識されない
[レベル2・・・通常行動]
決められた業務をこなし、何かする必要がある場合には、動くことができるので、目立った行動特性ではない
[レベル3・・・能動行動]
目的を持っていて、複数の選択肢からどうするべきかを決めて、自発的に業務を進めることができる
[レベル4・・・創造行動]
目標達成や課題解決のために、自発的的に行動できる
[レベル5・・・パラダイム転換行動]
今までにない発想や行動によって新たな価値を生み出し、自分だけでなくチームにいい状況をもたらせれる
レベル4~5が、行動特性が強いとみなされます。
そのため、コンピテンシーごとに段階別の基準を明確にしておくと、公正に評価できます。
ですが、レベルの高さだけを重視して優秀な従業員かどうか判断しないように注意する必要があります。
コンピテンシーモデルを活用する
面接やマネジメントなど、さまざまなシーンで、コンピテンシーモデルを活用しましょう。
例えば、採用の面接時に、応募者に質問にすると、コンピテンシーモデルと一致しているか確認できるため、自社に適した人材かどうかを判断できます。
コンピテンシーモデルを活用して、自社に適した人材を獲得しましょう。
コンピテンシーモデルの評価と改善をする
コンピテンシーモデルを評価し、改善しましょう。
よりいい変化があったのであれば、コンピテンシーモデルに問題はありませんが、目標を達していないのであれば、問題を洗い出し、改善する必要があります。
まとめ
コンピテンシーとは、ハイパフォーマーに見られる高い成果につながる行動特性のことです。
企業がコンピテンシーを適切に構築すると、人事評価や採用面接場で活用できます。
全従業員がわかりやすい目標に向かって、平等な評価を得られるために、コンピテンシーを活用してみてください。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
自宅の住所を仕事で使ってしまうと、自宅が知られてしまい、個人情報の漏洩やトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
そのような問題に巻き込まれたくない方は、バーチャルオフィスを活用するといいでしょう。
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。
月額300円から住所を借りれるため、オフィス費用を気にしないで、気軽に利用できるメリットがあります。
プライバシーをしっかり確保して、仕事や副業をしたい方は、ブルームを利用することをおすすめします。