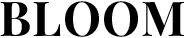稟議書とは?稟議書の必要性やメリット、書き方のポイントなどを解説
2025.06.19
多くの企業が、予算を決定する時に、社内稟議で承認を得るために、稟議書を使っています。
ですが、どうやって稟議書を書いたらいいのかわからないと悩む人もいるでしょう。
今回は、稟議書の必要性やメリット、稟議書作成時のポイントなどについて解説します。
稟議書とは
企業が意思決定をする時に、文書を回覧して関係者から承認を得るための手続きのことを稟議と言います。
稟議書とは、自分の権限では決定できない事案について、関係者の承認や決裁を得るために作成される文書のことです。
立案書とも言われています。
企業では、事案に対して決定権を持つ関係者の承認を得てから、意思決定をしますが、稟議のたびに関係者が集まることは、なかなか難しいです。
ですが、稟議書を活用すれば、関係者が集まらずに承認を得られるので、業務を効率的に進めることができます。
稟議書と決裁書の違い
決裁書は、稟議書と似ている言葉です。
稟議書は、関係者の承認を得るために、下位の承認者から順番に回覧されます。
ですが、決裁書は、稟議書の内容に対する最終的な判断を下すための書類で、決裁者が一人で決裁します。
つまり、稟議書は、事案に対する承認プロセスを進めるための書類ですが、決裁書は、最終判断をするための書類です。
稟議書と起案書の違い
起案書は、稟議書と似た役割があります。
起案とは、社内で実行したい事案やプロジェクトに関する原案を作ることで、起案書は、起案の際に作成した原案のことです。
稟議と起案は、原案を作って承認を得るという点で、似ています。
ですが、一般的に、起案は、事案やプロジェクトの最初のステップを意味しますが、稟議は、その後に承認を得るための手続きです。
とは言っても、稟議と起案を同義とするケースもあります。
稟議書を作成するメリット
稟議書を作成するメリットを挙げてみましょう。
会議を開く必要がなくなる
稟議書を作成すると、会議を開かなくて済みます。
稟議書を作成する目的には、高額物品の購入や大きな取引の締結などがあります。
そのため、経営者や役職者から承認を得るために、会議でプレゼンテーションをして、物品購入や取引の締結を認めてもらわなければいけません。
ですが、会議でプレゼンテーションをする代わりに、稟議書を使うと、会議のためのスケジュール調整などの手間がいらずに、承認を求めれます。
時間を短縮できる
稟議書を活用すると、事案に取り組むまでの時間を大幅に短縮できます。
関係者は、稟議書で事案の内容を事前に共有できるので、承認が得られ次第、業務に取り組めるのです。
急ぎの案件や重要な事案においては、稟議書を活用すると、迅速に対応できます。
稟議書を作成するデメリット
稟議書を作成するメリットについて見てきましたが、今度は、稟議書を作成するデメリットについて見ていきましょう。
作成するのに手間がかかる
稟議書の作成に手間と時間がかかる点がデメリットです。
文章を書くことが苦手な人や稟議書を作成したことがない人には、内容や書き方のことで迷ってしまって、他の業務のための時間が少なくなってしまうことがあります。
そのため、テンプレートを作って、負担を減らすようにするといいでしょう。
承認者の責任感が薄くなることがある
稟議の承認は、複数人によって行われるため、トラブルが起こった時の責任が明確でなくなり、承認者の稟議書に対する責任感が薄くなってしまいます。
また、承認のプロセスが多いと、内容を十分に精査しなくなる可能性があります。
稟議の問題が生じた際に、適切に対応できるように対処方法を整備することが重要です。
稟議書への記載項目
稟議書には、以下の項目を必ず記載します。
・決裁番号
決裁を管理するための決裁番号を記入する
・決裁日や起案日
決裁者と起案者が、決裁日と起案日を記入する
・件名
稟議内容を分かりやすく簡潔にまとめて記入する
・稟議内容
申請する稟議の目的や趣旨、何がいつまでに必要なのかを記入する
・金額
初期費用や月額費用など、必要な金額を記入する
・添付資料
外注する場合、契約内容が分かる契約書や見積書などを添付する
稟議書作成のポイント
稟議書を作成する際のポイントを挙げてみましょう。
目的を明確にする
稟議書の目的を明確で正確に伝える必要があります。
目的がわかりにくいと、稟議書が何の書類なのかが分からないからです。
また、目的が伝わらないと、否決されてしまうことがあるため、稟議の目的を明確にしてから作成しましょう。
要点を簡潔にまとめる
稟議書の文章は、要点を簡潔にまとめましょう。
だらだらと長い表現をすると、差し戻しになることがあるからです。
目的・背景・理由・メリットなどを明確に記載すると、承認者や決裁者が読みやすく、スムーズに理解できるでしょう。
根拠となるデータを添付する
根拠となるデータを稟議書に添付しましょう。
公的データのような信頼性の高い資料を添付して市場の状態や他社の動向を示すと、備品の購入や新規取引の契約の承認の必要性を承認者や決裁者に伝えることができます。
ですが、添付資料が多いと、重要な点が相手に伝わらなくなるため、説明に必要な情報を選びましょう。
メリットや課題も記載する
メリットだけでなく、課題やリスクも記載しましょう。
課題やリスクが稟議書に書かれてないと、承認者や決裁者から稟議書の承認を得ることしか考えていないと思われてしまいます。
そのため、稟議書に、取引することや購入することのリスクを示して、どうやって解決するのかを説明しなければいけません。
稟議書の記載例
稟議書
作成日: 2025年6月19日
起案部署: 企画部
起案者: 鈴木翔
件名: 企画部で使用するノートパソコンの購入について
稟議内容:
企画部で使用するノートパソコンを以下の内容で購入したいため、承認をお願いいたします。
背景・理由:
紙の資料を使うと、印刷するのに手間がかかってしまいます。
ですが、ノートパソコンを購入すれば、作業の負担が減って、仕事に効率的に取り組めるからです。
購入内容:
対象製品名: A社製 ノートパソコン
価格: 1台105,000円
数量: 4台(企画部員4名に1人1台貸与する)
導入効果:
ノートパソコンを導入すると、提案書作成に必要な1時間が、30分に短縮できます。
また、年間50,000円ほどのコストを削減できます。
使用開始希望日: 2025年6月19日
添付書類:
A社製 ノートパソコンのパンフレットや企画部員のアンケート結果
まとめ
稟議書とは、企業が物品購入や契約締結をするための承認を得るための書類のことです。
稟議書は非効率な面がありますが、現場での独断によるトラブルの防止や、会議の手間を削減するというメリットがあります。
スムーズに決裁を進めるために、必須の記載事項や書き方のポイントなどを押さえておきましょう。
コストを抑えて都心一等地で仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
働き方改革によって、場所を問わずに働ける環境が整ったため、バーチャルオフィスを利用する方が増えています。
東京は、バーチャルオフィスが一番多いエリアですが、仕事をする際に、東京は場所の優位性があるため、バーチャルオフィスの利用者も日本で一番多いです。
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所を貸し出しているバーチャルオフィスです。
ブルームでは、費用が、月額300円からという業界最安値のため、起業へのハードルが非常に低くなるメリットがあります。
また、西新宿は、日本有数のオフィス街のため、西新宿にオフィスがあると、顧客からの信頼を得ることができるでしょう。
低料金で、顧客からの信頼を得ながら事業を行いたい方は、ブルームの利用をぜひご検討ください。