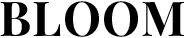フレックスタイム制とは?
2023.03.19
近年、従業員が働きやすい環境をつくるために、フレックスタイム制を導入する企業が増えています。
フレックスタイム制は、自由な時間に出勤できるというイメージがあるだけで、どんな制度かよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はフレックスタイム制について解説します。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、一定の期間に、あらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、勤務始業時間と勤務終業時間を労働者が自由に決められる制度です。
9時から17時のように勤務時間が固定されず、働く人たちが自分の都合に合わせて働き方を柔軟に調整できます。
そのため、仕事とプライベートのバランスが取りやすく、ワークライフバランスを推進するための取り組みとして、フレックスタイム制を導入する企業が増えています。
また、労働時間を効率的に配分することができるため、生産性や業務効率の向上にもつながると期待されています。
とは言うものの、フレックスタイム制であっても、自由に出退勤できるわけではありません。
フレックスタイム制を導入する際、企業は、1日の中で必ず出勤していなければいけないコアタイムという時間帯を設けることができます。
その前後数時間が、自由に出退勤できるフレキシブルタイムです。
従業員間のコミュニケーションや情報共有を円滑にするために、コアタイムを設けています。
1日の中で従業員が集まる時間帯がないと、ミーティングや商談をすることが難しいからです。
コアタイムの時間帯は企業によって違いますが、コアタイムが1日の労働時間とほぼ同程度になる場合や、フレキシブルタイムが極端に短い場合などは、フレックスタイム制とは認められないことがあります。
コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。
より自由な働き方ができるように、すべての労働時間をフレキシブルタイムとし、勤務時間から出勤する日まで、完全に労働者の裁量に任せている企業もあります。
コアタイムのない働き方は、スーパーフレックスタイム制と呼ばれ、こちらを導入する企業もあります。
フレックスタイム制を導入する目的
企業がフレックスタイムを導入する大きな目的は、従業員が仕事とプライベートのバランスを取りながら、充実感を持って働けるようにするためです。
フレックスタイム制を導入すると、自由で柔軟な働き方が実現しやすくなるため、ワークライフバランスが実現でき、通勤ラッシュの回避、メンタルヘルスの安定、残業時間の削減といった、さまざまなメリットがあります。
フレックスタイム制のメリットとは?
フレックスタイム制を導入することによって、従業員や企業にどのようなメリットがあるのかについて見ていきましょう。
通勤ラッシュを避けられる
フレックスタイム制のメリットとしてまず挙げられるのは、通勤ラッシュを避けられることでしょう。
満員電車やバスは、心身が疲弊したり、窮屈な思いをすることが多いので、通勤ラッシュがないと、快適に通勤できます。
早朝に出社して、オフィスに人が少ないうちに集中して仕事を片付ければ、業務の生産性や効率は高まります。
逆に、早起きが苦手な人なら、遅めの時間にゆっくり出社することもできます。
通勤ラッシュを避けつつ、最もパフォーマンスが上がるワークスタイルを組み立てられるのもフレックスタイム制ならではです。
プライベートの時間を多くとることができる
フレックスタイム制は、出退社の時間を自由に決められるため、プライベートの時間を自由にとることや、私的な用事に合わせてスケジュールを組めることがメリットです。
子育て中の共働き夫婦なら、保育園への送り迎えのために遅めに出社したり、早めに退社したりできます。
プライベートが充実すれば、気力や体力が充実し、仕事にもいい影響をもたらします。
フレックスタイム制をうまく活用すると、仕事でもプライベートでもよりよい時間を過ごすことができるでしょう。
定着率向上につながる
フレックスタイム制は、勤務時間を自分の都合にあわせて決められるため、従業員の定着率の向上につながります。
従業員が、プライベートの時間を確保しやすい職場は、従業員にとって魅力的な環境と言えます。
優秀な人材を確保しやすい
従業員は、フレックスタイム制の導入によって、育児や介護といったプライベートと仕事の調整を図りやすくなります。
そうすることで、家庭の事情によって退職しそうな人材を引き止めることができる可能性があります。
フレックスタイム制のデメリットとは?
メリットの多いフレックスタイム制ですが、デメリットもありますので、今度はデメリットを見ていきましょう。
コミュニケーション不足
フレックスタイム制度を導入すると、それぞれの従業員の出勤時間や退勤時間が異なります。
従業員同士で直接会う機会が減ると、情報共有がスムーズにできなくなくなる可能性が出てきます。
また、ミーティングは、参加する従業員が集まる時間帯にされるため、会議室の取り合いが起こる可能性もあります。
勤務時間外に仕事の連絡が来る
自分が働く時間は自由に決められますが、他の従業員の勤務時間と合わない可能性があります。
自分が退社した後に、取引先の担当者が働いていたら、退社後に電話やメールで連絡が入ることもあります。
フレックスタイム制を導入するときのポイントとは?
フレックスタイム制を導入する際には、どのような点に気をつけなければいけないのかを解説します。
就業規則と労使協定を決める
フレックスタイム制を導入するためには、始業時間と終業時間の労働者による決定を就業規則に規定しなければいけません。
また、労使協定において、対象となる労働者の範囲・清算期間・清算期間における総労働時間・標準となる1日の労働時間から構成される、フレックスタイム制の基本的枠組みを定める必要があります。
ICTツールを活用する
勤怠管理やスケジュール管理、そして、コミュニケーション不足の課題は、ICTツールの活用によって解決することができます。
勤怠管理システムを導入すれば、打刻が自動的に集計され、フレックスタイム制において複雑になりやすい勤怠実態や労働時間の把握や計算がしやすくなります。
まとめ
フレックスタイム制は、柔軟な働き方を可能にし、ワークライフバランスを推進する制度です。
うまく活用すれば、仕事とプライベートの双方を充実させることができます。
自分らしい働き方ができるように、制度の正しい知識を理解しましょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
ブルームでは、業界最安値の月額300円~、東京都新宿区西新宿の一等地住所がレンタルできます。
西新宿のビジネス一等地を会社や店舗の住所にできるため、仕事に対して高いモチベーションを維持できるでしょう。
また、住所が西新宿にあると、取引先にスタイリッシュな好印象を与えられるでしょう。
バーチャルオフィスの利用をお考えの方は、ブルームの利用をぜひご検討ください。