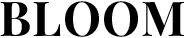360度評価とは?メリット・デメリットや注意点などを解説
2025.09.15
昨今、360度評価の導入をしている企業が増えてきています。
360度評価をうまく活用すると、さまざまな効果を期待できますが、やみくもに導入すると、逆効果になることもあります。
今回は、360度評価の意味や目的、メリット・デメリットなどを解説します。
360度評価とは
360度評価とは、上司、同僚や部下など立場が違う複数人の従業員が、評価対象者に多面的に評価をする評価方法のことです。
自分自身を客観的に評価することも含まれます。
上司が評価者になるのが一般的ですが、360度評価は、上司や同僚などさまざまな視点から、業務の成績や勤務態度の評価をするため、自己評価と他者評価の違いを知ることができ、公平で客観的に評価することができます。
360度フィードバックと360度評価は同じ?
360度評価と360度フィードバックは、基本的には同じです。
どちらも、上司、同僚や部下など複数の違う立場の従業員からフィードバックを得て、公正に評価されます。
360度評価は、評価に重点を置いていますが、360度フィードバックは、対象者の成長のためにフィードバックするというニュアンスが含まれています。
360度評価が求められる背景
360度評価は、評価制度の見直しが必要とされている現状によって、求められるようになりました。
近年、終身雇用が崩れて、勤続年数による評価ができなくなりました。
人材不足で一人の管理職が多くの部下を評価しなければいけなくなったり、人材の流動性が多いため、評価が難しく、評価者の負荷が高くなっています。
また、テレワークの普及によって、上司が部下の業務内容や結果のプロセスを確認する機会が少なくなったため、複数の従業員の視点を取り入れる360度評価が求められています。
360度評価の目的
従業員を客観的に評価して、組織の評価制度の公平性を高めることが、360度評価を導入する目的です。
従来、上司が部下の評価をしていましたが、上司の主観や人間関係に左右されることがあり、部下が正当に評価されていないと感じることがありました。
360度評価は、複数の従業員の視点を取り入れることで、評価の偏りを抑えて、納得できる人事評価を実現できます。
また、さまざまな立場の従業員が評価に参加すると、組織として評価すべき行動や成果のあり方を従業員間で共有できます。
360度評価のメリット
360度評価のメリットを挙げてみましょう。
客観的な評価ができる
360度評価には、客観的な評価ができるというメリットがあります。
従来、1人の上司が部下を評価して、報酬を支給したり、育成計画を決めていました。
評価項目や基準を決めていても、上司の主観が入りやすいので、適切な人事評価ができないといった問題が起こる可能性があります。
ですが、360度評価をすると、複数の従業員の視点から、部下の成果や行動を評価できるため、客観的に評価できます。
評価結果に納得しやすい
人事評価には公平さが求められますが、評価する上司と評価される部下の関係が、評価に影響を及ぼすことがあります。
ですが、360度評価では、複数の従業員が評価をするため、客観性が上がり、人事評価に納得しやすくなります。
管理職を育成できる
360度評価をすると、管理職を育成できるメリットもあります。
管理職は、部下に指示を出したり評価をしますが、自身の成果や行動へのフィードバックを受ける機会があまりないため、管理職として成長しづらい状況があります。
ですが、360度評価をすると、部下から評価をされて、自分を振り返る機会を得ることができます。
360度評価のデメリット
今度は、360度評価のデメリットを挙げてみましょう。
主観が入ることがある
360度評価は、従業員の主観によるため、相性が悪い従業員の場合、スキルや成果に関係なく、評価を得られないことがあります。
正しい人事評価をするために、評価者と評価対象者の関係が影響しない体制を作ることが重要です。
運用まで時間と手間がかかる
複数の従業員が360度評価をするため、多くの作業が必要になり、多大な時間と手間が費やされます。
そのため、従業員数が多い企業ほど、より多くのコストが発生します。
360度評価の導入方法
360度評価の導入方法を見ていきましょう。
360度評価の導入の目的と範囲を決める
360度評価を導入する時に、目的と範囲を明確にしましょう。
360度評価は、主に、人材育成、人事評価、コミュニケーションの活性化を目的にしています。
また、全従業員を評価対象にするのか、特定の役職に限るのかなど、範囲を決めることも大切です。
ですが、360度評価は、昇給や昇格などの公平な評価を得るために、全従業員に実施することが推奨されています。
運用ルールを決める
評価基準と運用ルールを策定しましょう。
評価基準や方法は、不正な評価や評価者間での公平性を保つことが大切です。
また、匿名式にするのか、記名式にするのかも決める必要があります。
匿名式は、率直な意見を引き出しやすいですが、感情的に評価されてしまうことがあります。
一方、記名式は、的確な評価が期待できますが、評価者間の関係が悪くなる可能性があります。
そのため、評価が感情や主観に左右されないために、全評価者に評価スキルを学ばせる研修を実施するといいでしょう。
運用方法を決める
評価の実施方法や媒体など、運用方法を決めましょう。
評価対象者や評価者が少ない場合、アンケート形式がおすすめです。
ですが、評価対象者や評価者が多い場合、時間と手間を省くため、オンライン形式にするといいでしょう。
また、オンライン形式による評価の効率性を高めるために、適切なシステムを選ぶことが大切です。
評価項目を決める
勤務態度や対人スキルといった、評価の目的にあった適切な評価項目を設定しましょう。
また、評価のばらつきを防ぐために、観察できる言動に焦点を当てると、正確な評価を得ることができます。
また、評価者に負担をかけないように、「評価できない」や「わからない」といった選択肢を設ける工夫も必要でしょう。
さらに、管理職にはマネジメント力、一般従業員には業務遂行能力など、役職や役割に応じた評価項目を設けるのもいいでしょう。
評価者と評価対象者を決める
評価者と評価対象者を選定しましょう。
評価者は、上司や同僚、部下など、評価対象者の行動や仕事ぶりを直接観察できる人物にすることが大切です。
評価対象者1人あたりの評価者の数は、5人~10人ほどが適切です。
管理職・同僚・部下のバランスを意識し、多様な立場の従業員を選んで、偏りのない客観的な評価が得られるようにしましょう。
スケジュールを決める
360度評価は、評価の集計や分析に時間がかかるので、あらかじめスケジュールを決めておきましょう。
導入前に、特定の部署でトライアル運用を実施して、スケジュールの問題や運用上の課題を洗い出すといいでしょう。
余裕のあるスケジュールにして、段階的に導入することが大切です。
従業員に周知する
従業員に周知してから、360度評価を導入しましょう。
評価の流れや目的、メリットなどを従業員に伝えて、評価対象者の不安を取り除き、制度への理解を深める必要があります。
従業員が評価の意義を理解できれば、きちんと回答してくれるでしょう。
個別対応の場を設けるのもいいでしょう。
360度評価についての疑問や不安が解消されると、制度への納得感が高まって、従業員同士の協力体制が強化されます。
360度評価の評価項目
360度評価の評価項目について見ていきましょう。
上司から部下・同僚から同僚への評価項目
上司から部下への評価や、同僚から同僚への評価では、実務やチーム内での貢献度に関する項目が設定されます。
具体的には、以下の項目が挙げられます。
主体性:自主的に考えて、行動する姿勢や積極性があるかどうか
実務遂行力:正確で効率的に業務をこなし、目標を達成できるかどうか
協調性:チームの従業員と良好な関係を築いて行動できているかどうか
課題解決力:自身で課題を発見し、適切に対処しているかどうか
論理的思考力:物事を論理的に分析して、判断できるかどうか
モチベーション:意欲的に仕事に取り組んでいるかどうか
部下から上司への評価項目
部下から上司への評価では、リーダーシップや組織運営といった資質が重視されます。
具体的には、以下の項目が挙げられます。
リーダーシップ:チームをまとめて、方向性を示せるかどうか
組織運営力:組織の仕組みや業務をスムーズに行っているかどうか
人材育成力:部下の成長を促すサポートをしているかどうか
判断力:状況を的確に見極めて、最適な意思決定をしているかどうか
業務遂行力:業務を効率的に遂行できるかどうか
360度評価を運用する際のポイント
360度評価を運用する際のポイントを見ていきましょう。
感情的に評価をしない
親しい人や付き合いがない人に関係なく、感情的に評価しないようにしましょう。
フラットな視点で見て、感情的に評価しないことが重要です。
360度評価の目的や基準を共有する
人事評価は従業員にとって重要なため、全従業員が納得できるように、目的や基準を共有することが大切です。
共有できていないと、360度評価のメリットを十分に発揮できないからです。
説明会で丁寧に説明して、質問や要望に真摯に対応するといいでしょう。
平均値を評価する
評価シートを集計する時に、評価者によって得点にばらつきが出ることがあります。
公平な評価をするために、最高点や最低点ではなく、平均値を使いましょう。
評価を匿名にする
評価を匿名にしましょう。
誰がどのような評価をしたのかが評価対象者にわかると、評価者に対して不信感を抱いたり、上司に気を使って高い評価点をつけることがあるからです。
フォローアップをする
フィードバックをしたら、フォローアップをしましょう。
フォローアップをすると、評価対象者が気づいていない点をアドバイスでき、改善のアクションの質を上げることができます。
上司は、360度評価の目標に対して、アクションを起こせているかを確認する必要もあります。
まとめ
360度評価は、従業員を多角的に評価するのに有効です。
上司や同僚、部下など、さまざまな立場からフィードバックを集めるので、公平性と納得感が高まり、今後も重要視されていくでしょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
ビジネスをするのに、活動拠点や登記する住所を、どの都道府県にするかは非常に重要です。
47都道府県の中でも、ビジネスに圧倒的に優位なのは、東京23区です。
東京23区には、多数の大企業が拠点を置いていて、信頼性が一番高いからです。
と言っても、起業したばかりの会社や個人事業主には、都心一等地に事務所を構えることはハードルが高いです。
ですが、バーチャルオフィスを利用すれば、都心一等地の住所を気軽に借りることができます。
また、地方在住者が、都心に会社や店舗を構えることもできます。
事務所の所在地を都心一等地にすると、クライアントから信頼を得ることができるため、ビジネスにおける優位性を確保できるでしょう。
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。
西新宿は、財閥系の高層ビルや東京都庁がある人気オフィスエリアです。
ブルームでは、月額300円~、西新宿の住所を借りれるので、高額なオフィス代を気にする必要がありません。
オフィス代をかけずに、仕事をしたい方は、ブルームの利用を検討してはいかがでしょうか。